エアコンは何畳用を買えばいいか悩みませんか?
カタログやネット販売を見ると、〇畳用と記載してありますが、本当にこの能力が適正なのか?
できれば能力が低い安いのを買いたいけど、部屋が冷えなかったり暖まらなかったらどうしよう。
そんな不安があると思います。
今回はそんな不安がある方に向けて記事を書いています。
- 適正なエアコンの能力(畳数)
- 適正サイズより能力up、downさせるメリット、デメリット
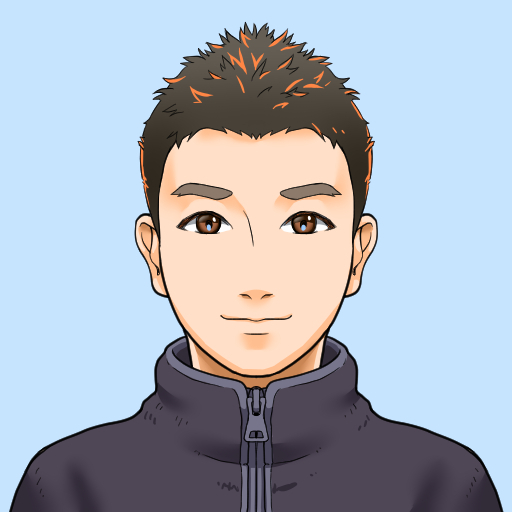
管理人:おすけぞー
- 建築設備機器の専門商社勤務(2007年~)
- 2級管工事施工管理技士
- 専門分野
空調機器:ダイキン工業
ダイキン製品の販売からサービス、技術的な問い合わせに対応。
家庭用エアコン・業務用エアコン・エコキュート・セントラル空調製品までダイキン製品を取扱しています。
適正なエアコンの能力
先に結論です。
カタログ記載の畳数より1つ下の能力が適正です
カタログ記載の畳数・能力は下記の通りです。2.2kwは6畳用、2.5kwは8畳用になっています。


本来、適切なエアコンを選定するには熱負荷計算が必要不可欠です。
熱負荷には大きくわけて7つあります。
- 通過熱負荷
- 日射負荷
- 外気負荷
- 照明負荷
- 機器負荷
- 人体負荷
- ※隙間風もあるが軽微のため除外
簡単に説明します。
通過熱負荷は建物の壁・屋根・窓ガラスからの熱伝達(温度差)によるもので、日射負荷は窓ガラスから入ってくる熱負荷(赤外線)です。
通過熱は壁の断熱仕様、面積、部屋の東西南北4面と接する面が外か部屋なのかで変わります。
日射負荷は窓ガラスの面積やガラスの仕様で変わってきます。
外気負荷は換気で外気を取り入れるため、その熱を処理するための負荷です。
照明負荷、機器負荷は部屋に置いてある電化製品から発する熱になります。
熱は機器からだけではなく、人体からも出ますので、何人が部屋にいるかも考慮します。
※暖房時は7つの内4つの日射・照明・機器・人体負荷はプラスに働きます。
夏であれば日中、冬であれば日の出前の朝方の1番負荷が大きい数値に安全率として、5%程度の余裕を見込んで機器を選定します。
もっと細かく言えば、寝るだけの寝室であれば、夏場の日中の最大負荷で選定する必要もありません。
この7つの負荷を考慮して計算すると、東京・大阪・名古屋・福岡のような気候で、築20年程度までであれば、ほとんどの戸建て住宅で1㎡あたり120wもあれば十分な計算になります。
マンションであれば1㎡あたり100wでも問題ないことが多いです。
最新住宅で断熱等級の高い物であれば、1㎡あたり60wも可能です。
新築住宅のエアコンの能力で悩んでいる方は、ハウスメーカーに熱負荷計算できるか確認してみてください。
1畳=1.62㎡です。
ではカタログ記載の参考畳数と能力を見ながら比較していきます。
ダイキンEシリーズ
| 機種 | 畳数 | ㎡換算 | 冷房定格能力 | 負荷 |
|---|---|---|---|---|
| S223ATES | 6畳用 | 9.7㎡ | 2.2kW | 1.16kW |
| S253ATES | 8畳用 | 13㎡ | 2.5kW | 1.56kW |
| S283ATES | 10畳用 | 16.2㎡ | 2.8kW | 1.94kW |
| A363ATES | 12畳用 | 19.4㎡ | 3.6kW | 2.33kW |
| S403ATEP | 14畳用 | 22.7㎡ | 4.0kW | 2.72kW |
| S563ATEP | 18畳用 | 29.2㎡ | 5.6kW | 3.5kw |
10畳部屋の冷房負荷は1.94kWなので、定格2.2kWの6畳用で問題ないという結果です。
暖房負荷は冷房負荷×1.2~1.4程度必要になります。
外気温度35℃の夏場に、室内温度を26℃にする冷房運転の場合は、室内外の温度差は9℃ですが、外気温度5℃の冬場に室内温度を23℃にするには室内外の温度差が18℃になります。
冬場の暖房運転は、夏場の冷房運転時よりも内外の温度差が大きく、熱が逃げやすいからです。
日射負荷・機器発熱負荷・人体負荷はプラスに働いていますが、外気温度差による負荷が大きいです。
1㎡あたりの負荷を1.4倍の168wで計算します。
| 機種 | 畳数 | ㎡換算 | 暖房定格能力 | 負荷 |
|---|---|---|---|---|
| S223ATES | 6畳用 | 9.7㎡ | 2.2kW | 1.62kW |
| S253ATES | 8畳用 | 13㎡ | 2.8kW | 2.18kW |
| S283ATES | 10畳用 | 16.2㎡ | 3.6kW | 2.72kW |
| A363ATES | 12畳用 | 19.4㎡ | 4.2kW | 3.26kW |
| S403ATEP | 14畳用 | 22.7㎡ | 5.0kW | 3.81kW |
| S563ATEP | 18畳用 | 29.2㎡ | 6.7kW | 4.9kw |
10畳部屋の暖房負荷は2.72kWなので、定格2.8kWの8畳用で問題ないという結果です。
冷房だけなら2ランク下、暖房を考慮すると1ランク下の能力になります。
カタログの参考畳数と実負荷での選定を比較して、なぜ異なるのか?ですが、カタログの畳数は断熱材なしの木造住宅で計算されているからです。
だから熱負荷が大きくなり、実際の熱負荷計算との差が出てきてしまっています。
カタログの畳数はこんなイメージ

実際のエアコンの使用状況
エアコンが運転している能力と割合を示したグラフを見てください。これはメーカーが約1万台のエアコンを調べた結果です。定格能力に対して50%未満で運転している時間が大半です。


各メーカーのカタログに記載してある畳数は無断熱の家を基準としているため、誰もが大きめのエアコンを購入していることがわかりますね。
またグラフからもエアコンを選定する際は、冷房よりも暖房を意識して購入する必要があるのがわかりますね。
定格能力比率として60%程度の効率が良い製品が多いため、電気代のことを考えてもカタログ通りの畳数としない方が良いでしょう。
適正サイズより能力up/downさせるメリット/デメリット
エアコンについて詳しい方や、よくカタログを見られている方は定格能力で見る必要があるの?と疑問に思う方もいると思います。
今のエアコンはインバーター機なので、負荷に応じて自動的に能力を変動させることができます。

上の画像はダイキンS223ATCS-Wの能力です。
暖房・冷房ともに定格能力は2.2kWですが、暖房時最大で3.9kW、冷房時最大で2.8kWの能力が出ます。
最大能力で考えると、14畳までの負荷は処理できることになります。
実際にできると思います。ただ私はおすすめしません。
それはデメリットが大きいからです。
能力を落とすメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・価格が安い ・本体が少し軽くて小さくなる可能性がある | ・風量設定が大きくなる ・運転音が大きくなる ・故障リスクが上がる ・電気代が高くなる ・空調に時間がかかる |
メリットは初期費用が安くなる事と、エアコン本体が少し小さいサイズになる可能性があることですが、デメリットはたくさんあります。
風量を最大にして能力を最大限に出す必要があります。余力がないため、暖めたり冷やすのに時間がかかります。
風量を大きくすれば、運転音が大きくなり、風を感じることで不快になります。
能力を最大限に出そうとすると故障するリスクもあがります。
インバーターエアコンは定格運転の60~80%近辺の効率が良い傾向にあるため、最大運転は非常に電力を消費します。
もちろん能力を上げた場合のメリット・デメリットもあります。
能力を上げるメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・短時間で空調できる(始動時) ・小さい風量で空調できる | ・価格が高い ・本体が少し大きくなる可能性がある ・電気代が高くなる可能性がある |
メリットは適正能力と比較して、暑い夏の帰宅時・寒い冬の朝方に短時間で空調できることです。
デメリットは本体価格が高くなる事、サイズが若干大きくなる事、負荷が少ないときに効率の悪いポイントでの運転となり、電気代が高くつく可能性があります。
始動時の空調についてはタイマー機能や遠隔操作を使えば解決できるので、メリットというには少し弱いかもしれませんね。
長くなりましたが、最初に書いた通りの結論になります。
カタログ記載の畳数より1つ下の能力が適正です
※寒冷地にお住まいの方で、暖房をエアコンでやりたい方は、寒冷地用エアコンをご使用ください。
